お米と日本の文化の関係は?

日本人の食の基盤となっているお米は、食べ物としてだけでなく神様に捧げる神聖なものでもあります。お米に感謝すると同時に、来年も豊作であるようにと祈りを捧げる儀式などは、現在も厳かに受け継がれています。
まず、お米が収穫される秋に、新米をお供えして神様に感謝する「新嘗祭(にいなめさい)」と呼ばれる儀式があります。新嘗祭は毎年11月23日に、天皇が行います。この儀式は飛鳥時代から行われており、とても重要な祭礼と位置づけられています。
秋の收穫が終わり、年を越して初夏を迎えると、いよいよ田植えが始まります。田植えのときに各地で行われるのが、「御田植(おたうえ)」や「花田植(はなたうえ)」と呼ばれる行事です。稲がよく育ち、豊かな実りが得られるようにと祈る行事で、着物に赤いたすきをかけた早乙女(さおとめ)姿の女性たちが苗を植える光景を、皇室や寺社が所有する田んぼで目にすることができます。
このほかにも、豊作を祈る伝統芸能に、「田楽」と呼ばれるものがあります。この芸能は田植えの前に、豊作を祈願する「田遊び」という行事がルーツとされており、平安時代の中頃から続いている古い芸能です。地域によって形式は異なりますが、お囃子に合わせて踊るなどの芸能が披露されます。
地域で行われる秋祭りなども、田の神様に收穫を感謝し、豊年を祈願するためのものです。
また、相撲も田植えととても関係の深い芸能で、格闘技だけでなく神事としての側面も併せ持っています。最も特徴的なのが、力士が踏む「四股(しこ)」です。これは元々、力が強く体が大きな力士が、大地を踏みしめて土の中の邪気を払い、豊作を願う神事でした。
このようにお米は、日本のさまざまな文化と密接につながっています。







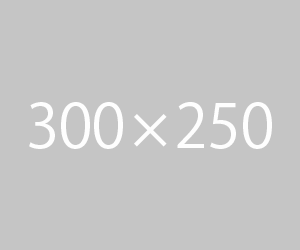



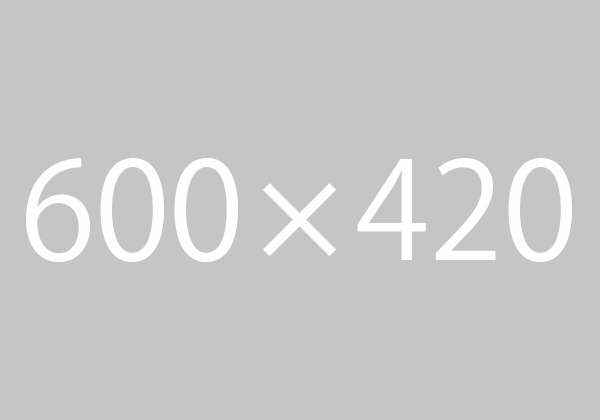
この記事へのコメントはありません。