お米と税金の関係とは?
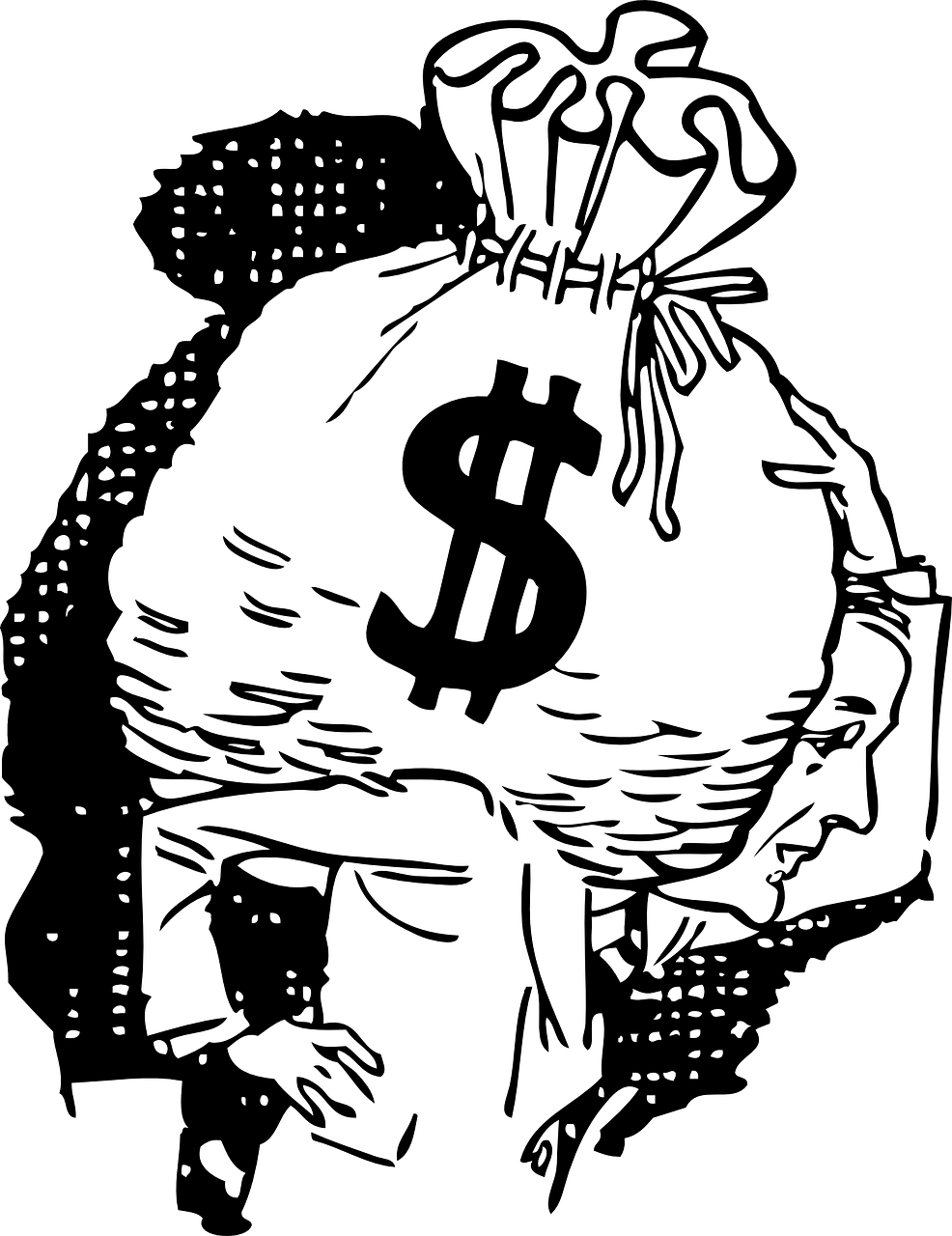
米が食や経済の基盤となって社会を形成してきた日本では、これまでさまざまな農地政策が行われてきました。最も古い記録で残っているのが、飛鳥時代(646年)に導入された口分田です。これは田収授法という法律よって、人々に農地を分け与える制度です。唐の均田制を参考にしたもので、6歳以上の男子に田約23アール、女子はその3分の2が支給されました。そして、その田んぼから収穫された稲の一部を税として徴収していたのです。
その後、大宝律令が制定(701年)され、税に関する法律が定められます。人々は良民と賤民という身分に分けられ、身分によって農地を分け与えられました。そして、これらの農地から収穫された稲を税として納めることを「租」と名付けました。
その後、安土桃山時代に、太閤検地(1582年)が実施されます。これは全国の農地の収穫量や年貢の量を調査して、これまで貫高という単位で現されてた生産高を、「石高」に改めました。さらに、これまで村ごとに税を徴収していたのを改め、農民一人ひとりから税を徴収するようになりました。
江戸時代に入ると、「新田の開発」が行われます。幕府や藩が新田を開墾するして、米の収穫量を上げる政策が進められたのです。
これまで税はお米で収められていましたが、明治時代になってお金で税を納める「地租改正(1873年)」が実施されます。
そして昭和時代に入り、第二次世界大戦で深刻な食糧不足に陥った日本は、米などを国が管理する「食糧管理法(1942年)」を施行します。これによって農家が国に米を差し出し、人々は国からの配給によって米を得るようになりました。
その後、糧管理法は廃止(1995年)され、現在では自主流通米を中心に米の流通が自由化されています。







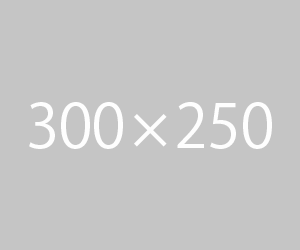



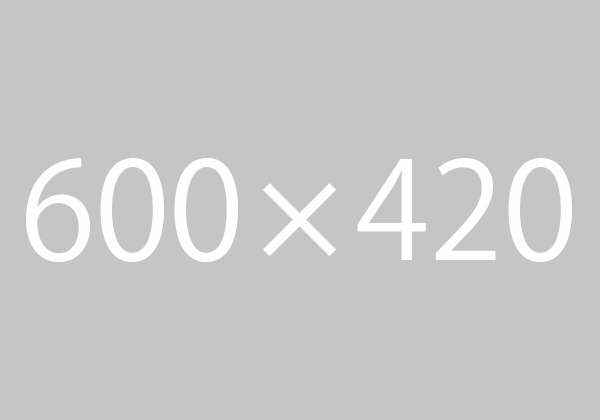
この記事へのコメントはありません。