分づき米と精米時に出る米ぬかの行方

米作り体験や精米体験などから食育を伝える自治体も増えています。米の稲穂の先についているのは「もみ」と呼ばれるものです。その皮(もみがら)を剥いて出てくるのが「玄米」です。食物繊維が豊富で普段の食卓に玄米を食べることもあります。
玄米は少し茶色味がかかっていますが、この色は「ぬか」の色なのです。白米にする際、精米を行っています。米の白の色になる作業です。なぜ精米をする必要があるのかという点についてですが、玄米のままだと噛み応えが強かったり、口の中でぼそぼそとすることから食べにくいと感じる場合もあります。ですので、精米をすることで食べやすさや癖の強さを取り除くことで食べやすい状態を作っています。
この精米作業ですが、「分つき米」といって、何割精米をするかということで風味の違いを出しています。5分つき米・7分つき米などがありますが、この数字が大きいほどに白米に近くなっていきます。「何分つき米なのか?」というところから好みの味を探してみるのも良いでしょう。
そして、精米時に剥がされたものは「米ぬか」と呼ばれています。この米ぬかはさまざまな使い道があり、例えば畑の肥料として活用することが可能ですので、捨てる必要はありません。肥料としても栄養価が高いという魅力があります。よく聞くぬか漬けの「ぬか」も米ぬかを使ったお漬物です。生野菜をぬかに漬け込むことによってさらに栄養価の高い状態で食べることができます。





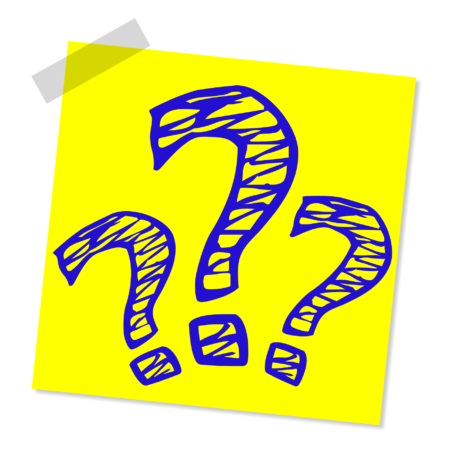
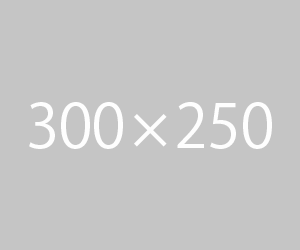



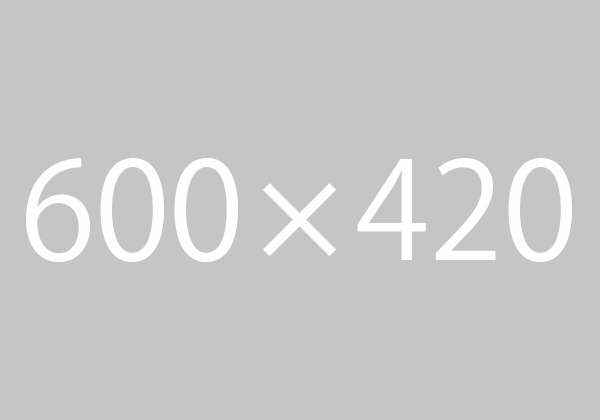
この記事へのコメントはありません。