日本のお米のルーツ

日本人の主食として長年愛され続けてきたお米。もともとのルーツは野生の稲です。栽培用として普及した稲が、現在の稲になったと考えられています。
お米は世界中でつくられており、稲を栽培している国は113か国以上にも上ります。栽培している国のうち、9割近くがアジアの国々です。お米を主食としている人が多いアジア圏における稲のルーツはとても古く、1万5000年以上も前に遡ることができます。
元々、栽培されていた場所は、次の2つの地域ではないかとされています。1つ目は、インドのアッサム地方からラオスの西部、タイ・ミャンマーから中国の雲南省あたりです。この地域からは、約3800年前の籾殻の化石が発見されました。2つ目は、揚子江の中流から下流にかけての地域です。ここにある遺跡では、9000~8000年前の稲の籾や茎などの化石が発見されています。
日本で食べられている稲が、どちらの地域から伝わったのかは詳しくわかっていません。しかし、およそ次の3つのルートで日本にやって来たのではないかと推測されています。
(1)揚子江から中国大陸を北上し、山東半島や朝鮮半島を経て北九州へと伝わったルート
(2)中国大陸をさらに北上し、遼東半島や朝鮮半島を経て日本へ伝わったルート
(3)揚子江下流から西九州へと伝わったルートです。
これらのルートもどれが正しいのかはまだ判明していませんが、いずれにしても中国から日本へとやって来たと考えられています。
日本では約2500年前の縄文時代に、稲作技術が伝来したことが、縄文時代を終わらせるきっかけとなり、弥生時代の幕開けになったとされています。



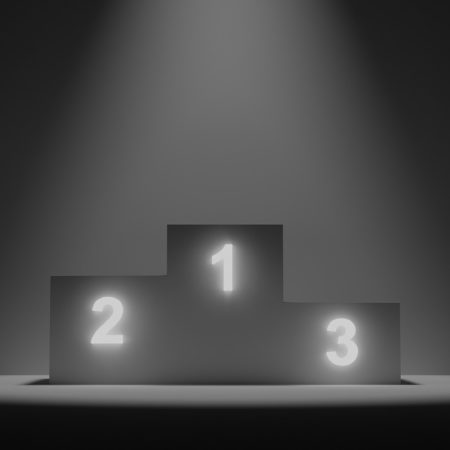


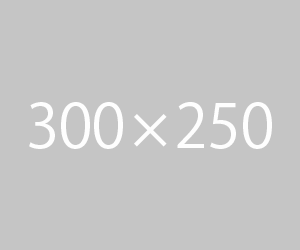



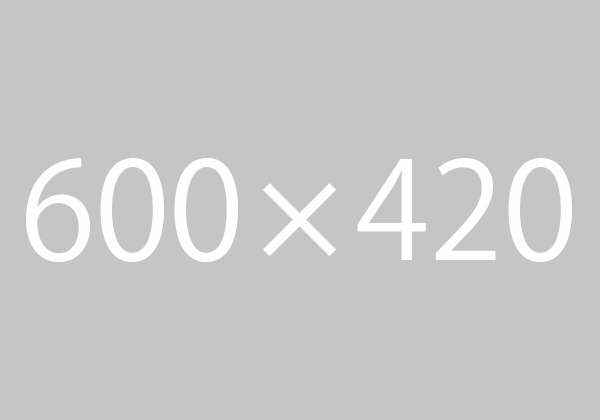
この記事へのコメントはありません。