日本における米作りの歴史とは?

米はアジアで作り始められたことから歴史が始まり、日本にやってきたのは約2000年から3000年前、九州地方に伝わったとされています。米作りは日本の高温多湿な気候に合い、安定収穫ができる上に保存可能といった好条件が重なり、各地方に広がりました。
当初の米作りは多くの人と力が必要で、人々はその場所に住み役割を分担し組織が生まれます。これが村ができるきっかけともなりました。米づくりの技術が発達すると同時に、米をどれほど所有しているかで村同士の力関係ができ、国としての形が整ったのです。
後に米づくりは国が計画をしそれに沿って作るようになっていきます。用水路や堤防さらには農具が開発されて生産量は増加し、田んぼの所有量や米の蓄えで格差が生まれたのです。そのために米作りに向かない地方は土地に適した米を作ろうと努力をしたのです。これが品種改良につながっていきました。
645年ごろに入ると、法律の下で田んぼが国有化され国民一人に対しての一定の田んぼの面積が与えられました。収穫した米は3%を税として納めることも義務付けられ、米が経済の中心になったのです。
1590年に入るとかの豊臣秀吉が太閤検地を行います。税金を正確に徴収するために田んぼの面積や生産量を調べる方法です。17世紀に入っても米は経済の中心で、米問屋や商人も誕生しました。1873年になって租税制度が改革され税金は米ではなく「お金」で払うようになり、現在のように本来の食べ物となりました。




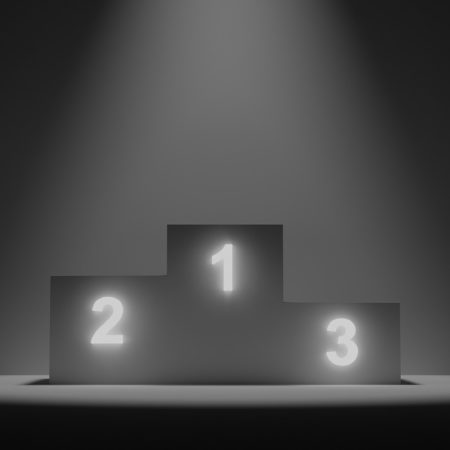


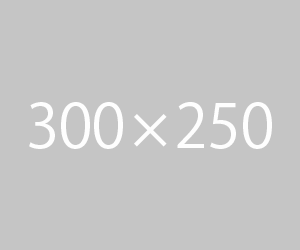



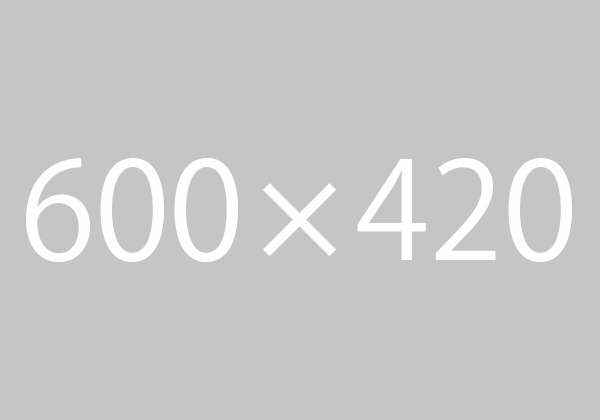
この記事へのコメントはありません。